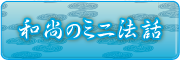和尚のミニ法話
畳の縁を踏まない
先日、教区のC寺様の恒規法要大般若会に随喜しました。維那(いの)という配役をいただき、本堂大間の両班位に就きました。維那という役は、大衆を指導リードする役で、法要中は挙経(こきょう:お経の題名を唱えること)、回向文を読み上げることが主な務めです。当日は付法要として合同供養上法事が一座ありました。読経中に参詣者の焼香があります。導師の脇を通って、着座している両班の寺方の前を通って焼香に出るわけですが、私は目の前を通り過ぎる方々の足元を何気なく見ていて気が付いたことは、畳の縁を踏まないように気を配っている方が数人おられたことです。女の方に多く、年配者だけでなく若い方の中にもそのような方がおられました。小さな子供さんの手を引きながら子供さんにもそのようにさせているお母さんもおられ、へえ~と感心しました。多くの方は平気で畳の縁を踏んで歩いておいででした。
昔は、特に神社仏閣や武家、商家の畳の縁には家紋が入っていて、縁を踏むことは先祖様や親の顔を踏むことと同じと考えられていて、生活のたしなみとして戒められていたようです。このような習慣は親や祖父母から言われ続けていないと身に付かないものです。「親の顔がみたい」といいますが、私は師匠からいわれてきませんでしたし、娘たちにほとんど言ってきませんでしたので、私も娘たちも平気で畳の縁を踏んでいます。他山の石として、C寺様から帰ってきた後、私だけでも踏まないようにしようと気に掛けています。
いつまでも あると思うな この命
「いつまでも あると思うな・・・」と言えば、下の句は「親と金」ですが、先日のお通夜法話では、「いつまでも あると思うな この命」としてお話しをさせていただきました。
私の場合、お通夜は「無常」をテーマに進めていきます。諸行無常、万物は流転する。仏教の根源的な捉えを皆様にわかりやすくお話ししています。このときにぴったりなのが梅花流御詠歌の「無常御和讃」です。 ♪人のこの世のはかなさは・・・・で始まるこの御詠歌を導師入堂の前にCDで流します。歌詞は印刷して皆さんに配ります。そして法話の時に歌詞の意味をかみ砕いてお話しします。
いつまでも未来永劫に続かないこの命なのだから、今この時に輝かせなかったらいつ輝かせるのか。輝かせ方はその人なりです。ある程度の齢を重ねてくれば、世のため人のために輝かせることも大事ですよ。とそんな話をしています。
関東のお通夜に行ったとき、お経が終わり法話をしようと振り返ったら親族の方しか残っておらず、参列の方は食事会場に移っていてびっくりしたことがあります。新潟ではありえないのですが地方によってさまざまです。お通夜は故人との最後の別れの式ですが、人の命の在りように想いをめぐらす機会でもありますので、参集の皆さんにお話ししたいです。そこで思いついたのは、お経の前に法話をするということです。これならば皆さんにきいていただけますもんね。葬儀屋さんとの打ち合わせでそう言うと、いい手ですねと感心していただきました。
新到掛搭式(しんとうかたしき)
大本山永平寺御用商のN写真館より封書が届き、新到掛搭式(しんとうかたしき)の集合写真と智玄さんの上山時の個人写真が送られてきました。(振込用紙も併せて入っていました。写真が不要なら送り返せというのですが。)
新到掛搭式というのは、簡単に言えば新入生入学式です。5月1日に式があったようです。この式を経てようやく新到和尚と呼ばれるのです。2月に上山しましたがそれまでは暫到(ざんとう)と呼ばれ一人前の雲水として扱ってもらえません。集合写真には70人ほどの新到さんが写っていました。この日を迎えるまでに相当な苦労があったことでしょう。智玄さんも10㌔痩せたとか。この日を迎えられずに下山した人もいたのでしょうか・・・。胸の前で叉手をして肘を横一文字に張る智玄さんの姿を見て師匠としてとてもうれしく思いました。背筋もピンと伸びていて威儀が整ってきたように見受けられました。ようやく修行のスタートラインに立ったわけです。がんばってほしいものです。
今は制中に入りました。今日は首座法戦式(しゅそほっせんしき)です。首座和尚が第一座となって大衆一如の厳しい修行が行われていることでしょう。いろんなことを見聞きして身に付けてほしいと願っています。
明日は富山市で梅花の全国大会。光照寺の講中から8名参加します。私はバス停までアッシー君です。
現代の”与作”は凄い
♪与作は木を切る、ヘイヘイホー♪ 「木こり」という言葉には、斧を木の根元に振り下ろす、昔ながらのイメージがありますが、どっこい!現代の木こりは凄いですよ。
今、庫裡の一部改修と住宅工事に併せて、本堂裏山の杉の大木を伐採しています。伐採は南蒲原森林組合にお願いしたのですが、そこの「特殊作業員」 の技が見事で目を見張ります。幹周囲3mもあろうかという大木を腰ロープと足の鉄爪でするすると登っていきます。チェーンソーで枝を打ちながら、写真のようにあんな上までいとも容易く(のように見えますが本当は大変な苦労なのでしょうが)上がります。そして、幹先をチェーンソーで切り落とします。その後地上に下りて、根本にチェーンソーを入れて切り倒します。倒れる時は凄まじい音がしますよ。彼の話では、枝をつけたまま切り倒した方がクッションになっていいのだけれど、倒す周囲を傷めることになるので、住宅に近いところではこの方法をとるのだとか。重機が近づけるところならば、重機で吊って幹上から切り落としてくることもできるのですが、大型重機が入らず、写真のクレーンも届かない場所なので。
彼らの格好もシャレていまして、欧米のチェーンソーメーカーの名の入った作業服とヘルメットを身に付け、レンジャー部隊というか海上保安庁海猿というか、そんな感じでかっこいいのです。そして何よりも彼らが若いということ。林業復活には、彼らの活躍が欠かせませんね。(まあ坊主の世界でも、青年僧侶がきびきびと動くのはかっこいいです。)
仏様の好物は
仏様へのお供えは、まずは香華灯燭(こうげとうしょく)。仏壇前机の中央に香炉(線香立て)を置き、左に花立て、右に燭台を置きます。これらを具足といい、写真のようにそれぞれ一つ置くのを「三具足」、花立てが二つ燭台が二つ計5基置くのを「五具足」と言います。特に、中央に香炉を置くことでわかるように、一番大切なお供えは「香り」なのです。仏様の大好物は香りだということです。普通は線香を立てますが、線香にもさまざまな香りのものがありますね。私は白檀系の香りが好きなのですが、人によってはきついと言われます。「ラベンダーの香り」とか「桃の香り」とかの線香がありますが、人工的な香りのものは好きではありません。
たまに、花とロウソクの位置を間違えておられる方があります。私は師匠から「砂糖桶」と覚えるのだと教わりました。仏様から見て、左に灯・右に華。つまり、さとううけ⇒さとうおけ⇒砂糖桶ということです。ところが仏様から見てというのを忘れて逆にすることがあって叱られたことがありました。
仏壇の前に座ったら、香華灯燭を弁備して、心を静かに落ち着けてから合掌してお参りいたしましょう。