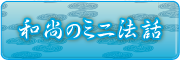和尚のミニ法話
帰山報告
今回は方丈様に代わりまして、智玄が帰山の報告をさせていただきます。
遅くなりましたが、ちょうど一か月前の3月9日に、福井県にある大本山永平寺より送行(そうあん:修行を終えて自分の師匠のお寺に帰ってくること)し、無事に帰ってまいりました。昨年の2月19日に光照寺を出発しましたので、丸一年と少しの間修行をしてきました。出発日のお見送りや6月の団体参拝で永平寺を訪ねていただいた皆様からの励ましのお声がけが、修行中の心が折れそうな時の支えとなりました。厳しい修行の中では精神が不安定になりがちですが、「応援してくれる人たちがいるから頑張らないと」と弱った心を強くしてくれました。
私のこの一年間を一言で表せば「感謝」です。在家からお寺に来て、何も知らない私に丁寧に教えてくださった師匠、長い間待っていてくれた家族、心配してくださった皆様、永平寺で共に修行した方々・・・すべての人に感謝しっぱなしの一年でした。多くの方の協力がなければ修行を続けることはできませんでした。
永平寺での修業は本当に貴重な体験でしたし、それができたことは幸せなことだと思います。振り返ってみて本当に永平寺の生活を体験できてよかったです。
私はこれからも「光照寺の若」として精進していく所存です。どうぞ末永く宜しくお願いいたします。(智玄)
海も偉いが水も偉い。 同事2
前回の記事中「海の水を辞せざるは同事なり。」について、言葉としてよく理解できないという声がありました。かつての私もそうだったのですが、「海の水を」と「辞せざるは・・・」と区切って解釈するからわからないのです。「海の」と「水を辞せざるは・・・」と区切ればおわかりでしょう。「海の」の「の」は「が」の意味ですからね。
さて、この一文は道元禅師の正法眼蔵第28巻「菩提薩?四摂法」の一節なのですが、「海の水を辞せざるは同事なり。」に続けて道元様はこう言われています。「さらにしるべし、水の海を辞せざる徳も具足せるなり。」と。水もそそぐ先のどの海がいいとか区別しないので徳を備え持っているのだということです。どうせ海に注ぐなら太平洋がいいとか日本海がいいとか言わないのです。
水も海も、自然界そのままの姿でいる限り、徳の大きさを私たちに示してくれています。私たち人間もその在り様のままの状態であれば仏そのものであると道元禅師はお示しです。そのままの在り様でないから心が乱れたり煩悩にさいなまれたりするのです。
同事とは一つになること、区別しないこと。心がけておきたいものですね。
黒スリと同事
黒スリとは黒いスリッパのことです。(なーんだ、ひねりもなにもなしですか。)永平寺をはじめとした修行道場では、雲水はこのスリッパを履いています。先日永平寺に団参に行った折り、智玄さんに頼んで知庫寮から拝請してもらいました。(買って届けてもらったということです。)
普段あまりにも俗世にまみれていますので、足元だけでも雲水気分に浸ろうという魂胆です。これを履いていると自分の修行時代を思い出します。古参和尚が黒スリで別の雲水を叩くのを見たことがあります。裸足なのでひび割れができて血で染まったことがありました。などなど。
白スリというのもあります。足の甲にかかる皮帯が白いのです。これは新到和尚がはきます。ですので一目で新到であるということがわかります。智玄さんは今は白スリです。上山したての頃は黒スリとすれちがうときはビビったそうです。
この程度の区別はそんなに深刻ではありませんが。勤務した中学校であまりにもくだらない区別がありました。1年生は白い靴下しかはけないとか、ジャージのファスナーを全開にしてはならないとか。今はさすがになくなっているでしょうね。
今年の管長猊下の告諭の骨子は「同事」です。みんなおんなじ。区別しない。差別しない。ということです。「海の水を辞せざるは同時なり。」海は信濃川の水は受け入れるが阿賀野川の水はいやだ、なんて言わないのです。それが海の徳なのです。
順現報受・・・モナラベンダーとバラ
住宅工事をしているとさまざまな方が出入りします。生コンを運んできた女性の作業員の方(今注目の土木女子「ドボジョ」です)の話です。
彼女が軒下に並べてあるモナラベンダーの鉢植えを見て、「これ何という名ですか」と聞いてきました。モナラベンダーは家内が好きで、挿し芽をしてたくさん増やしています。ラベンダーなのですがシソの仲間のようで、葉の裏が赤シソの葉によく似ています。夏の終わり頃から咲き出しますが葉も鑑賞に向いています。彼女に一通り説明した後、彼女の興味に応えたくなって一鉢差し上げようと思い、家内を呼んで選んでもらいました。女同士しばらく花談義をしていましたら、彼女が「バラを持ってきましょうか」と言います。私と家内は顔を見合わせてしまいました。と言うのは、境内にもバラの木がありピンクの花を咲かせていましたが、手入れが回らずほっておく状態でした。工事の機会に倒してしまったばかりなのです。そこへ「あげましょうか」と言われたものですから植える場所もないし上手く育てる自信もないので少し困惑してしまったのです。ですが、せっかく言ってくれる彼女に失礼で、家内はうまく断ることができないまま終わってしまいました。
「バラ持ってこられたらどうする」「いらないと言えばよかったね」「そんなこと言えるわけないでしょ」・・・というような会話をしていたら、玄関のピンポンが鳴り、家内が出たらなんと彼女がバラの花束をもっておいででした。私たちはてっきり根付きのバラの鉢植えのことだと思い込み「どうする?」などと困っていたわけですが、切り花だとは思いもよりませんでした。彼女はバラが好きで、庭にいろんな種類のバラを育てている様子でその何種類かのバラを花束にして持ってきてくれたのです。家内は大喜びでさっそく花瓶に活けていました。そして、たったさっきあげたばかりなのにすぐお返しを持ってきてくれた早さにもびっくりしました。「情けは人のなめならず」と言いますが、こんなに早く自分に巡り回ってくるとは。
仏教の根源的な考え方は因果応報です。今の自分の在り様は過去の因によるものであり、未来へ影響を及ぼすものである。自分の行いの影響力(結果)の現れ方は時間差があり、この世で結果を受けるのを「順現報受」、次の世で受けるのを「順次生受」、ずっと先の世で受けるのを「順後次受」と言います。
モナラベンダーという「因」がバラという「果」になってかえってきました。順現報受でしたのでうれしさ倍増でした。
永平寺参拝の旅
6月13日~14日、「大本山永平寺参拝の旅」に光照寺参拝団18人で行ってきました。まずは何よりもうれしかったのは、智玄さんが元気で出迎えてくれたことでした。痩せた身体はそのままでしたが足のケガも癒えつつあるようで、笑顔に出会えてホッとしました。妻である娘も安堵したようでした。背筋がピンとした立ち姿で、言葉使いも御山の雲水らしく、檀家さん方とも談笑している様子を見て上山4か月で大きく成長したなあと実感しました。「方丈様が一番うれしいみたい」と檀家さんに言われました。
「永平寺の山門をくぐる前に、大きく深呼吸してください。俗世とのしばしの別れですからね。私の修行が始まるんだという気持ちで。」とバス降車前に皆さんにそう伝えました。そのせいか、皆さん前向きで永平寺の生活を普段経験できない貴重な場として行じておられました。上山してから入浴、薬石(夕食)、坐禅、法話、紹介ビデオ視聴、開枕(就寝)で一日を終え、翌日は4時振鈴(四九日でしたので一時間遅れの4時起床でした)、朝の挨拶を副監院老師からいただき、法堂へ出向きます。階段が多くで大変でしたが、雨がふったためか明け方の木々や庭の苔が深い緑色で感動しました。法要中、供養をお願いしてありましたので焼香に出るのですが、私の後ろから黒い雲水が一人続いてきて、それが智玄さんであることがわかってびっくりしました。粋な計らいをしていただきました。続く楞厳会の時に、監院寮添茶があり私と妻と娘は監院寮に案内され、丸子副監院老師から親しくお言葉をかけていただきました。「緊張したー」と妻と娘。(私は楞厳会に会えなくてちょっと残念。)吉祥閣での小食(朝食)はおかゆではなくごはんでした。おいしかったです。典座寮の方々に感謝です。
生活の世話をしてくれた接茶寮の雲水さん、拝観案内をしてくれた伝道部の雲水さん、監院寮の方々、智玄さんのいる直歳寮の方々ありがとうございました。檀家さん方も皆さんが「来てよかった。貴重な体験ができた。また来たい。」と言っておられました。