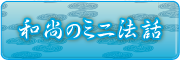和尚のミニ法話
大般若
6月18日(日)、教区寺院のご協力を得て大般若会が修行されました。礼仏七仏(らいぶつしちぶつ:仏様のお名前を唱えてお拝をします)、湯菓茶の伝供(とうかさのでんぐ:蜜湯、お菓子、お茶を本尊様にお供えします)の後、メインの大般若経の転読(だいはんにゃきょうのてんどく:経本をパラパラと流します)。参詣者は般若の風を受けにお寺方のそばに寄ってきます。身体堅固、無病息災を願います。この大般若経転読はなかなか難しく、コツが必要です。上手な人は手を高く挙げ、上から下へと大きく流します。(私は少し苦手です。)初めて見る方は興味深く見入っておられたようです。
梅花講のお花添えも重要です。法要中に「三宝御和讃」「花供養御和讃」「紫雲」「聖号」の4曲をお唱えしていただきました。きれいな声が本堂に響きました。
お天気も良く、仏の慈光功徳の風にあたり、心落ち着く一日でした。
ご参拝の方々、ありがとうございました。来年はもっと多くの方からのご参拝があるとありがたいです。
本堂の荘厳(しょうごん)
光照寺の大般若会の準備で大変なものの一つが、本堂の荘厳(しょうごん)です。丸柱に柱巻きを掛け、大間の上方四方に水引をぐるりと巻きます。高いところの作業なので梯子を使いますが、普通の梯子では高さが足りないので二連梯子を使います。これがけっこう重くて・・・。さらに高いところが苦手なものですから、一苦労なのです。しかし、今年は手伝ってくれる方がいましたので助かりました。「馬子にも衣装」で、年季の入った本堂も、美しく着飾って見違えるようです。
私たちの服装やお化粧もやはり、きれいに飾ってくれるものですが、時としてお似合いでない場合もありますね。気かざりすぎてゴテゴテであったり、センスが悪くて浮き上がって見えたり。気をつけたいもです。光照寺の荘厳は、まあそこそこなのではないかと思いますが。
お釈迦様の遺言ともいうべき「遺教経(ゆいきょうぎょう)」というお経の中にこのような一節があります。
『慚恥(ざんち)の服は諸々の荘厳に於いて最も第一なりとす。」
慚恥(ざんち)とは、恥を知る心と言いますか、己の至らなさに気づく謙虚な心、あるいは自分のあさましい言動を恥ずかしいことだと反省することです。
着飾るときには、この慚恥の服を真っ先に着なさいとお釈迦様は教えておられます。日々の生活を振り返ると、慚恥を忘れていることが多く、反省しきりです。
「遺教経」は、お釈迦様の最後の説法という意味合いから、亡くなったあとの枕経で読みます。また、釈迦涅槃の仏事でも読みます。
次の日曜日、18日が大般若会です。どうぞお参りください。おいしい精進おときを用意してお待ちしています。
タケノコと親孝行
今年はタケノコが豊作のようです。寺の山にはけっこう竹林があり、タケノコがにょきにょくと出ています。昨年が凶作でしたので、今年はと期待していましたらその通りのようです。
タケノコ料理はさまざまありますが、私は身欠きニシンや人参などの野菜と一緒に煮た味噌味の煮物が好きです。もちろん、タケノコご飯やみそ汁もいいですね。掘ってすぐの料理ならアク抜きする必要もありません。そうそう、ひき肉を挟んだはさみ揚げもいいですね。
当寺の大般若会が近づいてきました。5月18日(日)です。以前より「光照寺の般若はタケノコ般若」と呼ばれています。おとき料理にタケノコがふんだんに使われているからです。大般若会まであと10日間、お勝手の檀家さんは、「大般若まで出ているといいけどね。」と心配していました。
当地方のタケノコは孟宗竹です。孟宗といえば二十四孝。中国に伝わる、親孝行の二十四人の話です。孟宗の母親が冬にタケノコが食べたいと言うので、孟宗はタケノコを探しに竹林に入った。しかし、雪に埋もれた竹林にはタケノコが生えているはずもない。孟宗は悲しむであろう母親の顔を思い、天を見つめてはらはらと涙を流した。その涙が雪に落ちた。すると雪が解け地面からタケノコが伸びてきた。孟宗はこのタケノコを掘り、母親に孝行をすることができた。という話です。(ネットで検索すると、いろいろと探せます。福沢諭吉は二十四孝を批判している文をかいているようですが)
当寺の開山堂の前に衝立があります。衝立の絵が二十四孝の孟宗の絵です。墨が三本流れていますが、孟宗がタケノコを背負って持ち帰る場面の絵です。
タケノコを食すと親孝行をせねばと思いますが、なかなか・・・です。
春爛漫。花に蜂も蝶も。良寛の漢詩より
今日は気温が上がりました。上着を一枚脱ぎました。草花も元気よく咲き出しています。まさに春爛漫です。境内では、桜が葉桜となり、モクレンも花びらが茶色くなりパラパラと落ちだしています。代わって見事なのが「はなもも」です。赤紫というか濃いピンク色というか実にいい色です。
花無心招蝶 (花、心無くして蝶を招き)
蝶無心尋花 (蝶、心無くして花を尋ぬ)
花開時蝶来 (花開くとき 蝶来たり)
蝶来時花開 (蝶来たるとき 花開く)
吾亦不知人 (吾もまた 人を知らず)
人亦不知吾 (人もまた 吾を知らず)
不知従帝則 (知らずして 帝の則に従う)
良寛和尚の漢詩です。
花の周りを蜂や蝶が舞っているのを見ると、花も蝶も季節を忘れることなく、今この時に開き、今この時に飛んでくるのは、大自然の法則(帝の則)なんだと感じ入ります。
私と山伏さんの出会いも、そんな感じなのでしょうかね。(おおげさですね)
良寛の漢詩とはちょっと違いますが、今日の三条新聞に、当寺の永代供養墓の広告を掲載していただきました。これを見て、訪ねておいでになった方がいました。ご自分の先々のことが心配になったということでした。
写真は、鐘楼堂わきの「はなもも」。奥に散り姿のサクラ。
太鼓とほら貝のコラボ 地蔵講にて
地蔵尊の、年に一度の御開帳が三条新聞の記事に載ったことで、これをどなたかからお聞きになった山伏さんが,地蔵講当日にほら貝を手にしてお参りに来られました。私も初めて会う方です。白装束をまとい、そのものの格好をしておいででした。年の頃は70歳前後でしょうか。定年後に一念発起して高野山で修行されたそうです。思っても見なかったことで少しびっくりしました。法要をどうしようかと考えた結果、地蔵堂での巡堂の時に、私の太鼓にあわせてほら貝を吹いていただくことにしました。最初はちょっと微妙な感じでしたが、そのうちに何となく合ってきて「魂が通ずる」というのでしょうか不思議な感覚になりました。また、般若心経の読経では、錫杖の先っぽのような鈴でしょうか(名前がわからずすみません)、お経に合わせて鳴らしていただきました。私にとって初めてのおもしろく不思議な体験でした。参詣の方々はどのような感想を持たれたのでしょう。
おときを一緒にとお誘いしましたが、分水の「おいらん道中」を見たいからと去って行かれました。
山伏さん、来年もおいでくださいね。
写真は、地蔵堂巡堂での山伏さん。