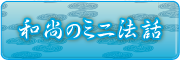和尚のミニ法話
「ご住職」より「方丈さん」でお願いします。
坊さんの呼び方というのは、一般の方にははなかなか難しいようです。
私ども曹洞宗では、住職のことを「方丈(ほうじょう)」と言います。一丈四方の部屋が住職の居間であることから方丈の間の和尚、略して方丈と呼ぶようになったのです。ですから、「方丈様」とか「方丈さん」と呼んでいただいてよろしいのです。というより、そう呼んでいただけるとうれしいです。
ところが、お若い方やお寺にあまり縁のない方は、この名をご存じないようで、「お寺様」とか「ご住職」とかおっしゃいます。確かにその通りなのですが、多くの方に覚えていただきたいと思っています。
(「方丈!」と呼び捨てにされる方もたまにおられます。ちょっとどうかなという気分にはなりますが・・・)
ご門徒の方は、「ご院住さま」と呼んでおられるようですね。
当山によくおいでになる業者さんで、仏具屋Hの社長さんは、「方丈様」と呼んでくださいます。仏壇屋Fの営業の方は「ご住職」言われます。「ご住職」はどの宗旨のお寺さんでも通用するからなのでしょうね。でも・・・。
ちなみに、当山には先代の住職もおりますが、「東堂(とうどう)様」とか「東堂さん」と呼んでいただきたいです。
(写真は、開山堂の天井絵の雲竜図です。けっこう迫力ありますよ。)
雪かき作務 ・・・ 修行の提要
1月9日の夕刻からの雪は翌日・翌々日と続き、けっこうな降雪となりました。1月11日は、朝課後2時間の雪かき作務でした。後から後から降る雪で、夕方にまた1時間の作務となりました。誰かに代わってもらいたい気もするし、明日に伸ばしたい気もしましたが、道元禅師の逸話を思い出し、雪かき作務に精を出しました。
道元禅師が中国で修行しておられる時の有名な逸話です。『夏のある日、用という名の老僧が庭で椎茸を干しているところに出会いました。強い日差しが照りつけ庭の敷瓦は焼け付くような熱さです。老僧は杖をつき、頭に笠さえかぶっていません。背中は曲り、長い眉は真っ白です。老僧は一心に椎茸干しの仕事をしています。いかにも辛そうに見えました。お年を尋ねると六十八歳との返事です。そこで私は「どうして若い者に頼まないのですか。」と問うと、「他はこれ吾に非ず(他人にやってもらったら、私がしたことにならない)。」と言いました。私は、「たしかにその通りですが、もっと涼しい時にやったらどうですか。」と尋ねると老僧は、「更にいずれの時をか待たん(今やらなければ、いつやるのか)。」と答えたのです。私は自分が恥ずかしくなって何も言えなくなりました。そして修行の在り様を思い知らされた次第です。』(駒沢学園編「道元禅師の典座教訓」より)
今日は少し寒気が緩みましたが雪本番はこれからです。
写真は、定点観測(1月16日の様子)。本堂の屋根雪が落下してけっこう積もっています。
今度、TVに出ます!
TVに出ることになりました。
BSN新潟放送の毎週金曜日午後2時50分からの「新潟名刹紀行」という短いスポット番組です。放映は、2月7日(金)です。
番組スポンサーの福宝さんの紹介で出演となりました。当寺の永代供養墓を福宝さんにお願いした縁でお話しをいただきました。
今日はあいにくのみぞれ混じりの天候でしたが、番組ディレクターさん、カメラマンさん、そしてお手伝いの方3名でおいでになり、伽藍の内外を撮影されました。
私にもインタビュー撮影があり、当寺の開山様のこと、地蔵様との縁や由来、地蔵信仰についてなどを話しました。少し緊張しましたが、「にこやかでよかった」とほめていただきました。
3分程度の短い番組ですので、どの部分が番組に使われるのか楽しみです。
檀信徒の皆様、どうぞ2月7日(金)、午後2時50分からのBSNテレビをご覧ください。
BSNは新潟の地方局ですので、県外の方は残念ながらご覧いただけません。トップページのお知らせに、撮影の様子の写真を数枚アップしますので、そちらをご覧ください。
ものもー、どーれ。
正月三が日は年始受けや年始回りでけっこう慌ただしく過ごしました。毎年のことですが、ゆっくりと箱根駅伝を見ることもかないません。一日は地元矢田の方たちを中心に年始客が大勢来ます。酒が入ってにぎやかになります。二日は吉野屋の方たちが年始に来ます。その後、寺の方からお供を連れて年始回りに出かけます。
さて、寺年始の仕方は、年始物を持った供が玄関を開けて「ものもー。矢田光照寺年始!」と励声に言います。するとそのお宅の家人は「どーれ」と返事をして出てきます。顔を合わせた後に「おめでとうございます。今年もよろしく・・・」等々の挨拶を交わします。
「ものもー」と言うのは、「もの申す」ということです。TVの時代劇に出てくる道場破りの「たのもー」みたいなものでしょうね。「どーれ」は「どれ、言ってごらんなさい」ということです。
「もの申す」と言うのですから「どれ聞きましょう」となって、玄関内で改めて「新年おめでとうございます。」となるのです。
ところが、寺方は今でも「ものもー」と言って入っていくのですが、「どーれ」と返してくれるお宅はほぼ皆無です。数年前までは数軒あったのですが、今年は全く聞かなかったとのお供の弁です。知らない方がほとんどなのでしょうね。
さらに、お供との挨拶が終わると、外に出てきて方丈と挨拶を交し合います。向こう三軒両隣がそれぞれ玄関先に出てきますので、互いに新年の挨拶を交わしてから、家に戻ります。
これも知らない方が多く、年始物を受け取るとさっと奥に引き込まれてしまう方が多くなってきました。外にいる私は、挨拶ができずに次のお宅に行くことになってしまいます。
伝え残していきたい風習ですが、時代の流れで消えていく運命なのでしょうか。
(写真は、光照寺の年始物。今年のマッチはこの色です。)
自未得度先度佗(じみとくどせんどた)
明けましておめでとうございます。拙ブログにアクセスいただきありがとうございます。更新はゆっくりですが、今年もどうぞお付き合いください。
「菩提心を発こす(おこす)というは、己れ未だ度(わた)らざる前(さき)に一切衆生を度(わた)さんと発願し営むなり」。これは、修証義第四章冒頭です。意味は、「仏の悟りを求める心を起こすということは、自分が救われる前に、すべての人々を救おうという願いの心を起こして行動をすること」です。これを簡単に言えば、「自分は後、他人様が先」ということです。これを、自未得度先度佗の心と言います。
年末の23日のことです。HさんとNさんから立派な門松をこしらえていただきました。お二人とも地域のために活躍しておられる方で、毎年、「親子門松づくり活動」を主宰しておられます。そのおこぼれを頂戴して当寺にも作っていただきました。竹の切り口が見事ですよね。
30日に本寺(雲居寺)様に行ったとき、Nさんが本堂前で門松を設置しておいででした。Nさんは雲居寺様の檀家です。Nさんは、「いや?、多くの方に頼まれてそちらを先に作っていたら菩提寺様のが今頃になってしまいました。申し訳なくてね。もっとも我が家のはまだ作ってなくて、明日の大晦日ぎりぎりになりそうですて。うちのは余った材料でこしらえますよ。」とおっしゃいました。
私はNさんのこの言葉を聞いて感銘を受けました。まさしく、自未得度先度佗の心、自分は後回しで他人様が先、を実践しておられる方だと思いました。
菩薩行そのものです。
門松のおかげでしょうか、よい正月を迎えております。皆様にとりましても、よい一年でありますように。