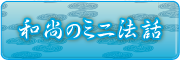和尚のミニ法話
あじさい開花始まる ・・・・花の役割り
写真:あじさいの開花がはじまってきましたよー。まだ6月になっていませんのに例年より少し早いような感じです。写真は「おりひめ」の開花の初期の初期。青い色がついてきました。この花はヤマアジサイの一種で分枝するので花がたくさんつく品種です。これからどんどんと青さが広がっていきます。
お近くの方で、何度もおいで可能の方は、「この花」と決めて開花の様子を定点観測されるのもよろしいかと。
果樹農家さんから聞いた話。モモやナシの花粉付け作業はとても大変だそうです。花粉がうまくついたかどうかは花を見ればわかるのだとか。花粉がうまくつくと花はポロポロと落ちるのだそうです。いつまでもおちない花があれば花粉がついていないと思われるのでつけ直しをするのだそうです。花の役割は実をつけるためにハチなどを呼び寄せ受粉させることにあるということですね。役割を遂行した花は自ら落ちていく・・・。改めて花の役割について思いを巡らす話でした。
この話を坐禅会の茶話会で話しましたら、ある方が、ウグイスの鳴き声も求愛目的なので、時季外れにいつまでも鳴いているウグイスは相手がいないお一人様ウグイスなのだとか。と教えてくれました。
私の役割は何なのでしょうか。そもそも人間に役割はあるのでしょうか。
二分の一玉のキャベツでいい時代
写真:ボランティア活動でのあじさい定植作業の様子。男性陣が法面に植え込んでくださいました。
野菜農家さんの話です。『例えばキャベツで、丸々一玉のものと二分の一カットのものとが同じ値段ならどちらを買いますか? 二分の一の方を買う人が結構いるのです。丸々一玉買っても腐らせるだけだし、明日は明日で違う料理にするから二分の一カットで十分なんだそうだ。核家族化が進み家族が少なくなってきているし、個食や孤食というのもあるしね。昔は「腐らせるのも消費だ」と言われていたけど、腐って捨てるにもお金のかかる時代だからね。』
「必要なものを必要な分だけ買う」が定着してきているようです。しかし、昭和世代の私はやっぱり丸々一玉の方を買ってしまいますね。
禅では夕食を薬石と言います。医食同源の考え方が根本にあります。薬も適量を越えて摂り過ぎれば毒になりますからね。
草取りボランティア活動
一昨日の日曜日、朝6時からの草取りボランティア活動では26人もの方から来ていただきました。「お寺がきれいになるのは檀家にとってもうれしいこと」とAさん。ありがたいことです。
檀家さんだけでなく坐禅会のメンバーも参加してくださいました。「作務は動の坐禅」とも言いますので、皆さん修行になりましたね。
1時間の作業でしたが、大勢の力というのはすごいもので、あっという間に裏庭をきれいにしていただきました。これで26日の大般若会はきれいな庭を眺めながらのいい法要になることでしょう。
あじさいの定植作業もしていただきました。植え込む場所がだんだんと無くなってきて、今回は30鉢の植え込みでした。今後、新たな場所を確保するために役員さんから雑木を切り倒し、山の斜面を刈り込んでもらって来年の場所をこしらえておこうと思っています。あじさい山も年々広く見事になってきています。
本当に皆さんありがとうございました。
「身だしなみ」は大切
「いつ、どこで倒れたり事故にあったりするかもしれないんだから、いつも身ぎれいにしておくんですよ。」と家内からよく言われます。「風呂に毎日入って、下着もきれいなものにして、それから・・・」とこと細かく具体的に言われています。「私が恥ずかしい思いをするんだから」とも。
このところ近所で、突然亡くなる方の知らせが続きました。元気だった人が病気が出て急に倒れたりしたケースです。不審死扱いで検死もあったとか。
そうなると家内の小言も、その通りだなと納得します。お化粧は身だしなみを整えることそのものです。ところが、高齢になってくると特に男性は身だしなみ(こぎれいにする)に気を使わなくなってきますね。かく言う私も「汚い、臭い」と言われても「それがどうした」という体で気に留めないことがままあります。困ったものです。
「心の身だしなみ」にも気を付けたいものです。
『慙恥(ざんち)の服は諸々の荘厳において最も第一なりとす」(遺教経)。 恥じること、恥ずかしいと思う心を身にまとうことはどんなきれいな服飾で身を飾ることより最も大切なことですよとお釈迦様はお示しです。恥じる心があれば、次はしないぞと明日への向上心が生まれてくるのです。
身と心とどちらもきれいにしたいですね。
写真:本堂の戸と上がり段、下足箱を塗装屋さんから塗り直しをしてもらいました。風雨と西日でかなり痛んでいましたので。お化粧したら見違えるようになりました。
認可参禅道場
光照寺の坐禅会も10年を越え、毎週日曜日6時からというのも定着してきました。参禅者も少しずつ増えてきていますので、これを機に参禅道場として宗門より認可していただこうと申請しました。この申請が通って晴れて曹洞宗認可参禅道場として登録されることになりました。写真にように看板札もいただきまして、本堂正面の柱に掛けました。4月20日発売の「月刊キャレル5月号」には朝活特集の中で当寺の坐禅会の様子を紹介してもらっています。目にされた方が道場の門をたたかれるやも知れません。改めて身の引き締まる思いです。
さて、このところの作務は境内の草取りです。いたる所が草で青々としてきました。草の伸びも早いのでついていくのはしんどいです。
本日の作務中に一句読みました。
「花散りて 庭のスギナの 根の深き」(良秀)
オープンガーデンのガイドブック作成のクラウドファンディングは19日が最終日。まだ目標金額に届いていません。お気持ちのある方、どうぞよろしくお願い致します。
https://camp-fire.jp/projects/view/748184?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show